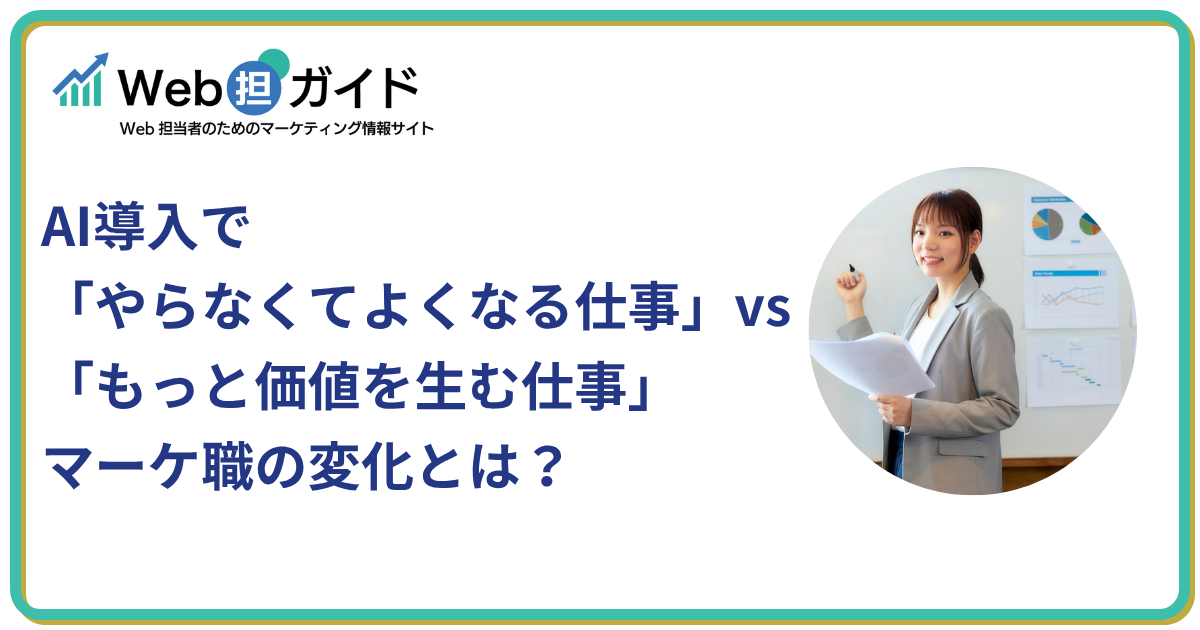こんな課題をお持ちのWebマーケティング担当者向けの記事です
BtoB企業のWebマーケティング担当者やコンテンツマーケティング担当者の以下の課題にお答えする記事です。
- AIの登場でマーケティング業務がどう変化するか知りたい
- AI導入で減らせる業務や今後重要になる業務を知りたい
- AIを導入する際に覚えておくべきポイントを知りたい
この記事では、AIによって変わるマーケティング職の役割や、人間とAIの得意な業務の違い、マーケターとして今後磨くべきスキルについて詳しく解説します。
そのほか、BtoB企業のAI導入事例やAI活用時の注意点など、BtoB企業がコンテンツマーケティングでAIを活用をする際の概要については、こちらの記事をご覧ください。
-
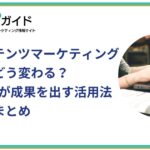
-
AI×コンテンツマーケティングで業務はどう変わる?BtoB企業が成果を出す活用法と注意点まとめ
BtoB企業のWebマーケティング担当者やコンテンツマーケティング担当者の以下の課題にお答えする記事です。 生成AIを活用して自分の業務を改善したい どんなツールが実務で使えるのか知りたい マーケティ ...
目次
AIによって変わる「マーケ職の役割」
AIで代替可能な領域-情報収集・資料作成・記事のたたき台など
AIの導入により、コンテンツマーケティング業務の中でも「定型化されたインプットやアウトプット」を伴う作業などでは自動化が進んでいます。
AIが得意とするのは、パターン化された情報の整理や構造化であり、
- 競合調査や市場分析のリサーチ結果を要約
- 営業資料やホワイトペーパーの初稿を短時間で生成
といった作業は、AIに任せることで効率が格段に上がります。
また、以下のような作業も、精度の高いアウトプットが期待できる領域です。
- ブログ記事やメルマガのたたき台作成
- SNS投稿のアイデア出し
これらは、人間が行うと時間がかかる一方で、パターンやルールに基づいて反復可能な作業であるため、生成AIに任せることで工数を大きく削減できます。
たとえば、記事作成において「○○というキーワードでSEO記事の構成案を作って」といったプロンプトを入力すれば、わずか数分で構成案や本文のたたき台が出力されます。
これにより、リサーチやライティングの時間は確実に短縮できるようになりました。
ただし、AIが出力する情報はあくまで一般論や既知のデータに基づいたものであり、「文脈を読む」「本質的な問いを立てる」といった部分は人間の力に頼る必要があります。
人が担うべき領域-戦略策定・ブランド設計・ユーザー理解など
AIが業務の一部を肩代わりするようになっても、コンテンツマーケティング担当者が手放すことができない業務があります。
それは、以下のような戦略的な思考を必要とする領域です。
- マーケティング戦略の策定とKPI設計
- ブランドのポジショニング
- ペルソナ設計やカスタマージャーニーの設計
- 顧客分析(インサイト)の深掘り
これらの業務では、ユーザーの感情や社会背景、時代性を読み取ったうえで、「どう伝えるか」「どう差別化するか」を判断する必要があります。
このような文脈依存性の高い業務は、AIだけでは対応しきれません。
また、AIが合理的な選択肢を提示しても、それを「誰が、なぜ、どう実行するか」を決めるのは人間であり、組織内での調整や説得、部門をまたいだ合意形成といった人間関係の中で進める業務も、マーケターの重要な役割のひとつです。
マーケティング担当者が「やらなくてよくなる仕事」とは?
定型作業・繰り返し業務(例:メルマガ文案、下書き記事、レポート初稿)
マーケティング業務には、日々の中で繰り返し発生する「定型業務」が数多く存在します。
AIの導入により、これらの業務は真っ先に「やらなくてよくなる仕事」として対象となります。
■メルマガの文案
配信目的やターゲット、商品特徴などを与えれば、複数案を瞬時に生成してくれるため、ゼロから人間が考える手間を大幅に減らせます。
■記事コンテンツの下書き
対象となる読者や記事コンテンツを作成する目的などを指示すると、テーマに沿った内容で見出し案や本文を出力させることができます。
■レポートの初稿
調査したいテーマだけでなく、目的や出力する形式を指定するだけで、インターネット上の情報から適切な情報を探し出し、レポートとしてまとめることができます。
さらに、アンケート結果の要約や、バナー用コピーの案出しのように一定のルールやパターンに基づくアウトプットは、特にAIと相性の良い領域です。
このような作業は“人の時間”を浪費しやすい反面、AIには向いているため、効率化・自動化の余地が大きい領域です。
AIの方が得意な業務の例
単に「やらなくてよくなる」だけでなく、「人間よりAIのほうが優れている」と明確に言える業務も存在します。
AIのほうが得意とされる業務には特徴があります。
- 入力データが明確かつ大量にある
- 出力がパターン化・定型化しやすい
- 作業量やスピードが評価軸になりやすい
たとえば、SEO記事の構成案をキーワードから導き出したり、トレンドや競合に関するデータを効率よく収集・可視化するような作業です。
ほかにも、FAQやレビュー要約といったフォーマットが定まった文章の生成や、A/Bテストの結果パターンから示唆を導き出す分析なども得意領域です。
さらに、広告文やキャッチコピーの案を複数提案するといった“発想支援”にも優れたパフォーマンスを見せます。
また、AIはルールとパターンに沿ったタスクを高速で処理するのが得意です。
特に、ChatGPTやClaudeなどの生成AIは、ユーザーの指示に応じて即座に複数の提案を出すことができるため、企画やキャッチコピーなどの精度を上げる「壁打ち」など、発想の起点や比較材料を得るためにAIを活用することもできます。
こうした業務をAIに任せることで、人間は「考える」ことに時間とエネルギーを使えるようになります。
マーケティング担当者が「もっと価値を生み出せるようになる仕事」とは?
インサイト発見、戦略立案、クリエイティブの方向性決定など
AIが定型業務を担うのに対し、マーケターが力を発揮すべきなのが「価値を生む仕事」です。
中でも、ユーザーの本音を深掘りし、それに基づく戦略を立てるといった業務は、人間ならではの強みが活きる領域です。
具体的には、以下のような業務が該当します。
- ターゲットの潜在ニーズや課題の洞察(インサイト)発見
- 市場環境や競合状況を踏まえたマーケティング戦略の立案
- 商品・サービスの訴求軸やコンセプト開発
- クリエイティブ施策(コピー・ビジュアル)の方向性検討
これらは単なる情報処理ではなく、「なぜこのアプローチが有効なのか」「このタイミングでどう訴求すべきか」といった文脈理解と仮説思考が求められます。
特にインサイトの発見については、ユーザーインタビューの声のトーンや間の取り方、言葉選びなどを感じ取る「人間的な感性」がなければ導き出せないため、AIでは難しい領域といえます。
ユーザーとの関係構築とストーリー設計
顧客との関係性を深めるためには、単発的な施策ではなく、一貫したメッセージやブランド体験の積み重ねが不可欠であり、マーケティング活動において重要なのは、「短期的な成果」だけでなく、ユーザーとの長期的な関係性をいかに築くかという視点です。
たとえば、ブランドの世界観を軸にしたコンテンツを継続的に発信したり、接点ごとに最適な体験を設計することによって、ユーザーの記憶に残るストーリーを形成していきます。
ストーリーは「誰に、どんな価値を、どのような流れで伝えるか」が重要であり、これには、共感を生む言葉選びやビジュアルの統一感、時代背景との整合性など、人の感性が大きく関わってきます。
自社独自の視点・判断が求められる業務
AIはあくまで「与えられた情報に基づく出力」を行うツールであり、自社のビジネス特性や戦略目標に基づく判断を下すことはできません。
そのため、自社のビジョンにあったマーケティング計画や成果指標の優先順位付け(リードやコンバージョンの獲得を重視するか、アクセスを増やす施策をとるか)など、自社独自の視点が必要な業務は、マーケティング担当者が責任を持って計画立案する必要があります。
また、クライアントや他部門との調整、経営層への提案といった「文脈の深い判断と対話」が必要な場面では、AIよりも人間の判断力・言語力・感情知性が求められます。
マーケターが磨くべきスキルセットとは?
AIと協働するためのプロンプト設計力
AIを活用する際に大切なのは、AIに対して適切な指示を出せる力、「プロンプト設計力」です。
たとえば、ChatGPTに記事の構成を依頼するときでも、「どのような読者に向けた記事か」「どのようなトーンで書くか」「どんな視点や要素を含めるか」といった情報を具体的に与える必要があります。
対して、抽象的な指示では期待した内容が得られず、質問や指示を繰り返す必要が生じます。
プロンプト設計力として必要なのは、以下の3点です。
- AIが理解しやすい文脈や条件を与える力
- 欲しいアウトプットを逆算して問いを立てる力
- 出力結果に対して評価や修正を加える力
つまり、「AIの能力を引き出せる人」が、これからのマーケターの強みになります。
戦略的思考、ユーザー理解、データリテラシー
AIが登場し、今後ますます重要になるのが、戦略的思考とユーザー理解、そしてデータリテラシーです。
戦略的思考とは、目先の施策にとらわれず、事業全体の目標や組織方針との整合性を考慮して判断を下す力です。
また、ユーザー理解の力も不可欠で、単なる属性データではなく、ペルソナの感情や背景まで想像できる深さが求められます。
さらに、AI時代にはデータリテラシーも重要です。
AIの出力結果を鵜呑みにせず、背景となる前提やバイアスを見抜き、適切に活用する力が、マーケターの判断の質を左右します。
これらの力を掛け合わせることで、マーケティング施策の精度と再現性を高めることができます。
コンテンツ設計力と「伝える力」
生成AIがコンテンツの素案を出してくれるとはいえ、最終的に「どんな構成で、どんな順序で、どう見せるか」を決めるのはマーケティング担当者であり、コンテンツ設計力や伝える力を磨く必要があります。
たとえば、AIが生成した記事をそのまま使っても、ユーザーの状況に合わなければ読まれません。
コンテンツの中で、どの情報を際立たせるか、どの順序で伝えるか、どこで感情を揺さぶるかといった編集力・表現力が、読者(ユーザー)との解像度の高い接点をつくる鍵になります。
AI時代のコンテンツマーケティングでは、構成編集のセンスと伝わる言葉の感覚が、これまで以上に重要になります。
社内での役割をどう再定義するか?
「AI管理者」ではなく「AI活用戦略家」へ
マーケティング担当者としてAIを活用する場合、与えられたタスクについてAIで効率化するだけではなく、より高い視座として「AIをどう活用すれば成果につながるかを設計する人」へと進化することが望まれます。
「とりあえずAIを使う」のではなく、「AIによって、マーケティング戦略全体をどうアップデートするか」を描ける人になることで、組織にとって不可欠な存在になります。
業務の中でどのようにAIを活用するかの全体戦略を考える際は、次のような観点が重要になります。
- どの業務領域でAIを活用するのが最も効果的か
- 活用するAIツールの選定と評価
- 社内でのAI活用ルールやガイドラインの整備
- AIと人の役割分担の設計
- 成果指標の再定義(量より質の評価軸など)
ただツールを使うのではなく、目的に合わせて活用し、その効果を検証・改善するという視点を忘れないよう注意しましょう。
また、AIを活用したマーケティング業務の最適化についてはこちらの記事も併せてご覧ください。
-
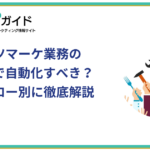
-
コンテンツマーケ業務のどこをAIで自動化すべき?マーケフロー別に徹底解説
BtoB企業のWebマーケティング担当者やコンテンツマーケティング担当者の以下の課題にお答えする記事です。 コンテンツマーケティングでAIをどのように活用できるか知りたい 各工程(業務)での代表的なツ ...
チーム全体でのスキル転換が求められる
AIの活用は、個人のスキルだけでは完結しません。マーケティングチーム全体として、役割とスキルの再構築が必要になります。
たとえば、以下のような変化が考えられます。
■ライター
これまで「文章をゼロから書くこと」が中心だったライターは、今後AIで記事コンテンツを作成する場合、出力したコンテンツに関する編集者としての視点が求められます。
構成の最適化やファクトチェック、トーン&マナーの統一といった、読者体験の品質を高めるスキルや、精度の高いコンテンツを作成するためのプロンプト設計力やAIを活用したリサーチスキルも必要となります。
■アナリスト
単なるデータ集計やレポート作成はAIが得意とする分野であり、アナリストにはその先の「なぜそうなったのか」「次にどうするべきか」といった洞察力が求められます。
AIから得たデータをどう読み解き、施策に落とし込むかについて、仮説思考とビジネス理解を掛け合わせた、より解釈力のある分析者への進化が求められます。
■ディレクター
AIに任せる部分と人が担うべき部分を切り分けるなど、チーム内外の連携を最適化するマネジメント力が求められます。
また、複数のAIツールを適切に選定・運用するためのリテラシーや、成果のモニタリング・改善の仕組みを整える役割が重要となります。
上記の通り、単に「一部の人がAIを使いこなせるようになる」だけでは不十分です。
チーム内でAIを活用する体制づくり、ナレッジ共有、ガイドラインの整備などが重要です。
また、マーケティング部門だけでなく、営業・商品企画・カスタマーサポートなど、他部門との連携においても、社内での「共通言語」としてAIの理解度を高めておくことで、部署を越えた連携や提案もスムーズになります。
まとめ:AI時代のマーケターに必要なのは「変化をデザインする力」
AIの進化は、コンテンツマーケティング担当者にとって避けられない変化ではありますが、それは「職を奪う脅威」ではなく、むしろAIツールは人間の思考や表現を補い、拡張するための強力なツールです。
これまで多くの時間を費やしていた定型作業をAIに任せることで、本来注力すべき「価値創造」にエネルギーを注げるようになるなどのメリットがあります。
AIには代替できず、担当者自身が注力すべき業務としては、ユーザーの心をつかむ企画力、共感を生むストーリーテリング、チームを巻き込む推進力などが挙げられます。
また、AIを壁打ちとして活用することで、自分ならではの視点や得意分野を磨くことも可能です。
AI時代のマーケターに求められるのは、どう業務効率化できるかという点だけでなく、マーケティング戦略をどう最適化するかなど、より高い視座に立つ視点です。
ディレクターバンクでは、オウンドメディア運用をはじめとしたBtoB企業に対するコンテンツマーケティングのお手伝いを行っております。
「オウンドメディア運用でAIを活用したいがどのツールを使えばいいかわからない」などお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
Webマーケティング視点で成果を上げるためのLPやホームページを制作します
ディレクターバンク(株)のWeb制作は、即戦力のWeb制作ディレクターがWebマーケティング視点で成果を上げるためのホームページやLPを制作。
公開後の運用、改善もワンストップで対応します。